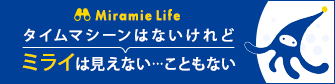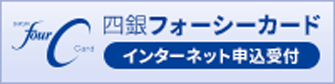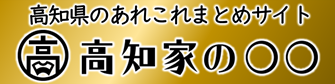![]() マネー
マネー
今後の節税対策に
贈与税が改正された?以前からの変更点や相続税との関係もわかりやすく解説!
2023/8/31

2023年度の税制改正では、贈与税の暦年贈与制度と相続時精算課税制度で重要な変更があります。この改正により、生前贈与による節税方法が大きく変わるでしょう。この記事では、暦年贈与制度、相続時精算課税制度の変更点と相続税との関係、今後の節税対策について解説します。
暦年贈与の改正

贈与税の課税方式には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの種類があります。ここでは、暦年課税制度の改正の内容やいつからの贈与が対象かなどについて、わかりやすく説明します。
暦年贈与と生前贈与加算
暦年課税では受贈者(贈与を受ける人)1人につき、基礎控除額の年間110万円までなら贈与税がかかりません。この仕組みを利用した贈与を「暦年贈与」といいます。110万円を超えた贈与では、その超えた部分(200万円の贈与なら90万円)に対して贈与税が課税されます。将来、贈与者が亡くなったとき、生前贈与した財産は相続財産には含まれません。
死亡の前3年以内の贈与は相続税の対象に
贈与を受けた日の3年以内に贈与者が亡くなった場合、生前贈与はなかったことになり、相続税の課税対象になります。この法律上の規定を「生前贈与加算(持ち戻し)」といいます。
たとえば、親が2023年6月15日に亡くなった場合、3年前の2020年6月15日以降の贈与が持ち戻しの対象となるのです。生前贈与加算は、被相続人が亡くなる直前に駆け込みでの贈与による、相続税の回避の防止が目的です。
生前贈与加算では贈与財産は相続時の時価ではなく贈与時の時価で持ち戻され、生前贈与で納めた贈与税があれば相続税から控除されます。
生前贈与加算が相続開始3年前から7年に延長
2023年度税制改正では、生前贈与加算の対象期間が3年から7年に延長されます。ただし、延長した4年間の贈与のうち、100万円までは相続財産に加算されません。
| 前3年以内の贈与 | 全額相続財産に加算 |
| 相続開始3年より前で7年以内の贈与 | 総額100万円を超えた部分を相続財産に加算 |
| 相続開始7年より前の贈与 | 加算対象外 |
適用されるのは2024年以降の贈与からのため、2027年以降に発生する相続から持ち戻し期間が加算されます。 たとえば、2031年4月1日に亡くなった人の生前贈与加算は、以下のようになります。
・2024年4月1日から2028年3月31日までに贈与した財産:100万円を差し引いた金額を持ち戻す
・2028年4月1日から2031年4月1日までに贈与した財産:全額持ち戻し
相続時精算課税制度の改正

次に、相続時精算課税制度の改正について解説します。
相続時精算課税制度とは
60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫が贈与を受けた場合に、2,500万円まで贈与税が非課税になる制度です。2,500万円を超える贈与の場合、超えた部分に対して一律20%の贈与税がかかります。贈与者が亡くなったとき、贈与された財産は全て相続財産に加算され、相続税が課税されます(納付済みの贈与税は控除される)。
つまり、贈与者が亡くなる何年前の贈与であろうと、相続財産として持ち戻されるわけです。相続財産が基礎控除(3,000万円+(600万円×法定相続人の人数))以下の人で、贈与された財産が2,500万円以内であれば、相続税も贈与税もかかりません。
贈与者ごとの選択制
相続時精算課税制度は暦年課税との選択制であり、贈与者ごとに選択できます。
たとえば、父からの贈与は相続時精算課税制度を利用し、母からの贈与は暦年課税の選択も可能です。ただし、一度選択したらその贈与者については暦年課税に戻せません。
相続時精算課税制度を利用するには、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日に必要書類を添付して、贈与税の申告書を提出しなければなりません。
相続時精算課税制度に年110万円の基礎控除を新設
2023年度税制改正では、相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が加わります。2024年以降に相続時精算課税制度を選択した場合、年110万円までなら贈与税がかからないだけでなく、相続税もかからないのです。
また、改正前は少額の贈与でも申告が必要でしたが、年110万円までの贈与は申告も不要となります(年110万円を超えると期限内申告が必要)。
現状ではメリットの薄い相続時精算課税制度
相続時精算課税制度では2,500万円以内の贈与の時点では贈与税はかからないものの、最終的には相続税がかかるため、課税の繰り延べとなるだけです。そのため、現状では相続時精算課税制度の利用は贈与税課税人数の約1割と、利用が広がっていません。
相続時精算課税制度の目的は、親世代から子世代への早期の資産移転による経済活性化であると考えられます。改正により制度のメリットが大きくなることで、利用の拡大が期待されます。
贈与税改正後はどうすればいい?

今回の贈与税改正によって、これまで有効とされた節税対策ができなくなるなどの影響が考えられます。最後に、税制改正後に効果のある対策を紹介します。
暦年贈与と相続時精算課税制度のどちらを選択すべき?
相続時精算課税制度に110万円の基礎控除が新設され、相続税の基礎控除を超える財産がある人にも節税効果が見込めるようになります。今後、暦年贈与と相続時精算課税制度のどちらが有利になるかの目安の1つに、贈与者の年齢があります。
生前贈与加算の7年を超える時間のある人とない人
たとえば、生前贈与を検討する時点で余命が長くないと考えられる高齢者の場合、相続時精算課税制度の基礎控除を利用するとよいでしょう。亡くなる直前の贈与であっても年110万円以内なら、基礎控除の範囲であれば相続税も贈与税もかからないからです。
これに対して生前贈与加算の7年を大きく超える時間がある人は、暦年贈与の基礎控除を利用してより多くの資産を移転するとよいでしょう。
値下がりしている財産を贈与する
生前贈与は、対象となる財産が値下がりしているタイミングで行いましょう。相続時に生前贈与の財産が持ち戻される場合、暦年贈与でも相続時精算課税制度でも贈与時の価額を相続税の課税価格に加算します。たとえば、1株1,000円の株式を生前贈与して、相続時に1,500円に値上がりしていたとします。この贈与が生前贈与加算に該当した場合、1株1,000円の評価額で相続財産に加算され、1,500円で加算されるより低い金額ですむのです。
つまり、株式や土地などの評価額が変動する財産は、安値のときを見計らって贈与すると相続税を抑える効果が期待できます。
収益を生む財産を早めに贈与する
賃貸アパートなどの収益を生む財産は、早いうちに贈与するほうが有利です。家賃などの収益分によって親の財産が増えると、子の相続税負担も増えます。しかし、早めに子に贈与すれば収益も子が受けることになり、親の相続財産も増やさずにすむわけです。
このような生前贈与は相続税の節税だけでなく、お金を必要とする子世代が財産を有効活用できるメリットもあります。
まとめ
暦年課税の生前贈与加算の期間が3年から7年になり、相続時精算課税制度に年110万円の基礎控除が新設されました。これにより、相続時精算課税制度が暦年贈与より有利になるケースも考えられます。どちらの制度が有利になるかはケースバイケースですが、早めに方針を決めて実行に移しましょう。
(提供元:Mattrz![]() )
)
【おすすめ記事】
住宅ローンの仕組みとは?借入手続きの流れ&審査のポイントを押さえよう
NHK朝ドラのモデル植物学者・牧野富太郎博士と老舗酒蔵「司牡丹酒造」を繋ぐクラフトジン「マキノジン」