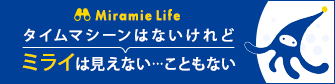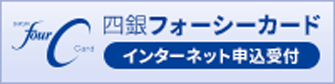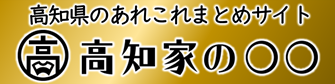![]() 経済
経済
Bankers Talk Simply About ヨノナカ
株式会社ガンダム?
~持続可能な発展:社会的インパクト編~
2023/9/20
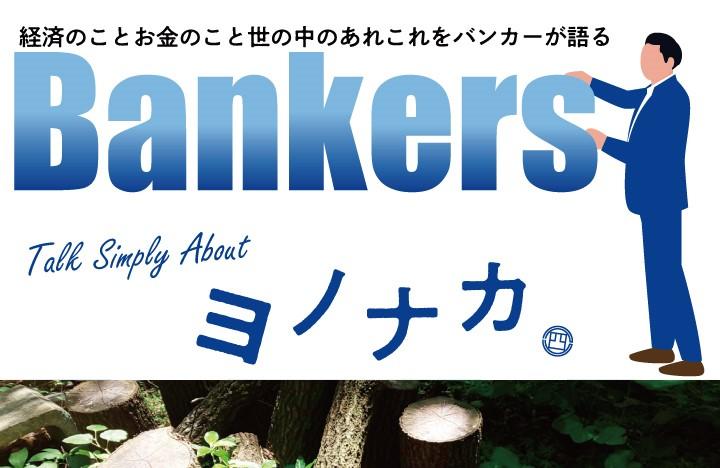
機動戦士ガンダムは、私と同じ1979年生まれのアニメシリーズです。現在放送中の最新作『機動戦士ガンダム 水星の魔女』では、なんと「株式会社ガンダム」なるものが作中、設立されます。
「アスティカシア高等専門学園」生たちが、その経営に当たり、ロボット兵器であるガンダム開発のために軍事転用されてしまった医療技術GUND(ガンド)を、本来の目的である医療の世界で役立てようとがんばります。学生ベンチャーですね。
ガンダムシリーズは、モビルスーツと呼ばれるロボット兵器を駆使して、宇宙・地球を舞台に戦争が繰り広げられる、というのが基本的に共通した設定ですが、この人気シリーズにおいて、学生が株式会社を設立するというシナリオが採用されていることに、時代の空気を感じます。
会社と社会
我々が会社に所属する理由について聞かれれば、まずは「収入を得るため」と多くの方が答えるのではないでしょうか。
来年(2024年)、新しい1万円札の「顔」になる渋沢栄一さんは、『論語と算盤(そろばん)』という著書において、損得勘定(算盤)と道徳(論語)という、一見かけ離れて見えるものを一致させることが重要である、そうでなければ、生まれた富は永くは続かないと説きました。会社と社会は、漢字こそひっくり返っていますが、価値観までもがひっくり返るようではイケない、ということだと私は理解しています。
インパクト投資
金銭的な収益だけでなく、社会的な便益(べんえき:お金で評価し切れない価値も含みます)を、事業評価の新しい指標にしよう、それを「(社会的)インパクト」と呼ぼうということが、日本だけでなく、世界共通の考え方として、重視されるようになってきています。
その代表選手が、前々回、ご紹介したtCO2(トンシーオーツー)です。
【Bankers Talk Simply About ヨノナカ】 発展のモノサシ:お金 × CO2~持続可能な発展~
また、前回、ご紹介した格差の問題では、極度の貧困状態にある人をなくす、ゼロ人にする、この「人(にん)」がインパクトを測定する指標・単位となります。
【Bankers Talk Simply About ヨノナカ】お金、何円持てる?~持続可能な発展:格差編~
ですから、たとえば、同じく100万円、儲かりそうな事業機会があったときに、CO2が減る方、貧困解消につながる方が、優れた事業であり、優れた投資機会である、という、なんだか、とても当たり前のようにも思えますが、それをきちんと、数字で評価できるようにしたり、何らかの工夫をして「見える化」していこう、という取組みが始まっています。
実際、岸田内閣では、昨年(2022年)のSDGs推進本部会合で、「インパクト投資」という、社会課題の解決への貢献と、投資収益の両立を目指す取組みを推進する姿勢を示しました。民間の投資資金が、環境問題や貧困問題といった社会課題の解決に使われるようになるのであれば、これほど素晴らしいことはないように思えます。
多様なインパクト
たとえば、CO2を減らすためには、再生可能エネルギー、すなわち、太陽光発電や風力発電が有効である、とされています。しかし、太陽光発電設備を設置するために、新たに森林を切り開いた場合はどうでしょうか。
石炭火力で賄っていた電力を、太陽光発電に置き換えれば、たしかにCO2排出量は減るでしょう。しかし、森林自体がCO2の吸収源ですし、それ以外にも、地下水の蓄積、様々な生き物の住処、土砂災害の防止など、森林には、様々な機能があることが知られています。
それでは我々は、そうした森林の価値の保持と、太陽光発電への置き換えによるCO2削減という価値+電力販売で得られるお金、果たして、どちらを選ぶべきなのでしょうか・・・
(なお、様々な条件によっても変わってはきますし、数年単位での時間がかかるようですが、太陽光発電設備の製造・設置時の排出量を考慮してもなお、石炭火力から太陽光発電への置き換えによるCO2削減量は、同面積の森林によるCO2吸収量を上回るという試算があります)

トレードオフ:あちらを立てれば、こちらが立たぬ
「社会的インパクト」というものを考えるときには、一つのインパクトについてのみ考えたのでは不足で、その事業が及ぼすインパクトを多面的に評価する必要があります。環境・防災面だけでなく、たとえば、それが、地域の人にとっては、精神的に大切な森であった場合、森がなくなってしまうことの文化的なインパクトも考慮するべきでしょう。
SDGsでは、17のゴール、そのどれかを達成するために、他のどれかを犠牲にすること(トレードオフと言います)は認められていません。気候変動を止めるために、海や陸の生き物の多様性を犠牲にしてはイケないし、経済発展の結果、格差(≒相対的貧困)が拡大するようではイケない、という考え方です。
よかれと思ってやったこと、社会のためと思って開発した技術でも、意図せざる結果=インパクトをもたらしてしまうことがある、という悲劇は、経済成長と環境・格差だけではなく、科学と戦争との関係・歴史にも当てはまります。
環境・格差・疫病・戦争といった、今のヨノナカの持続可能性を脅かす諸問題に対して、お金と科学技術という善も悪もない道具を最大限に活用し、人類の叡智で乗り切ろう、というのが、インパクトという考え方、SDGsという人類共通のゴール、脱炭素というムーブメントです。