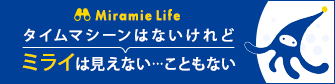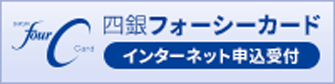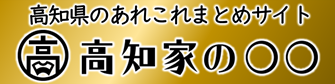![]() 経済
経済
改正内容や対応のポイントを解説
「電子帳簿保存法」とは?改正概要や対応ポイント、対象者をわかりやすく説明!
2023/8/21

2022年1月1日に、電子帳簿保存法が改正されました。この改正により、法人も個人事業主も2023年12月末までに電子取引における電子データの保存に対応しなければなりません。この記事では、2022年1月の改正内容や対応のポイントをわかりやすく解説します。
※本記事は2023年5月18日時点の情報をもとにしております。
※(参考資料)国税庁電子帳簿保存法に関するパンフレット
電子帳簿保存法の改正内容

電子帳簿保存法は、国税関係の帳簿や書類を電子データで保存する方法について定めた法律です。最初に、2022年1月に施行された改正の概要を解説します。
事前承認手続きの廃止
2022年の改正によって、事前承認制度が廃止されました。改正前は、電子帳簿等保存とスキャナ保存をするには、3カ月前までに税務署への承認申請が必要でした。今後は申請を行わなくても、電子データ保存を導入できます。
タイムスタンプ要件の緩和
タイムスタンプとは、刻印されている時刻にその電子データが存在していたことと、その時刻以降に対象のデータが改ざんされていないことを証明する仕組みです。
改正前はスキャナ保存または電子取引の際、受領者の自署とおおむね3営業日以内のタイムスタンプ付与が必要でした。その条件が緩和され、さらにデータの変更の履歴が記録される(または変更できない)システムを採用していれば、タイムスタンプの付与そのものが不要になります。
改正後は、書類の受け取り後のタイムスタンプの付与期間が最長2カ月と7営業日に延長され、受領者の自署も不要になりました。
検索要件の緩和
改正前は電子取引の際には、電子的に保存したデータを一定の条件で検索できるようにしておく必要がありました。
改正によって、検索項目は「取引年月日・取引金額・取引先」に絞られています。また、税務職員によるデータのダウンロードの求めに応じられる場合には、以下の検索機能の確保が不要になりました。
- 日付または金額の範囲指定
- 2項目以上の任意の項目を組み合わせた条件
検索項目が3つだけになり、検索設定の手間が軽減されました。
適正事務処理要件の廃止
改正前に書類のスキャナ保存で必要だった、以下の改ざん防止の適正事務処理要件が廃止されました。
- 相互けん制(事務処理を2人以上で行うなど)
- 定期的な検査
- 再発防止策の社内規程整備等
電子取引における電子データ保存の義務化
申告所得税および法人税における電子取引の取引情報について紙での保存が廃止され、電子データ保存が義務化されました。ただし、2023年12月末までは宥恕(ゆうじょ)期間とされ、一定の要件を満たすと、紙での保存も認められます。
令和5年度税制改正大綱における猶予措置
「令和5年度税制改正大綱」により2024年1月1日以降も以下の2つの条件を満たす場合は、電子取引データを単に保存することが可能とされました。これにより、改ざん防止機能や検索機能の要件に沿った対応が不要になります。
- 保存時の要件に従って電子取引データを保存できない相当の理由があると税務署⻑が認めた
- 税務調査の際に電子取引データのダウンロードおよびプリントアウトした書面の提示・提出の求めに応じられる
罰則規定の強化
今回の改正では規制緩和もありましたが、スキャナ保存されたデータに関連した不正があった場合の罰則が強化されました。電子データの隠蔽や仮装された事実があった場合に、その事実において生じた申告漏れ等に課せられる重加算税が10%加重されます。
また、電子取引でデータを紙で保存するなど電子保存していない場合、青色申告の承認が取り消されるおそれがあります。
電子帳簿保存法の対象者と対象文書

ここでは、電子帳簿保存法の対象者と、対象となる文書を確認しておきましょう。
電子帳簿保存法の対象者
電子帳簿保存法の対象となるのは、国税に関する法律により国税関係帳簿書類の保存をしなければならないとされている者です。法人税を納める法人や、所得税を納める個人事業主が該当します。事業規模の大小は関係ありません。
電子帳簿保存法の対象文書
電子帳簿保存法の対象となる文書は、以下のとおりです。
国税関係帳簿
国税関係帳簿とは、以下のような帳簿が該当します。国税関係帳簿は電子データでの保存、紙での保存を任意で選択できます。
- 仕訳帳
- 総勘定元帳
- 補助元帳
- 現金出納帳
- 売上台帳
- 買掛金元帳
国税関係書類
以下のような決算関係書類と取引関係書類を、国税関係書類といいます。国税関係書類も電子データでの保存、紙での保存を任意で選択できます。
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 試算表
- 棚卸表
- 請求書
- 見積書
- 納品書
- 領収書
電子取引
電子取引とは取引情報の授受をデータで行う取引のことです。以下のような方法で取引情報をやり取りした場合、電子取引に該当します。電子取引の取引情報は紙での保存は認められず、要件を満たしたデータ保存が義務付けられます。
- 電子メール
- ホームページ
- EDI取引
- クラウドサービス
電子帳簿保存法への対応のポイント

電子帳簿保存法が改正されても、中小企業や個人事業主がすべての書類を電子化するのは難しいと考えられます。まずは2024年1月に向けて、電子取引の電子データ保存に対応していきましょう。
自社の現状を確認する
自社で行われている取引や経理の各種書類が、どのような形式で保存されているかを確認します。さらに、電子取引に該当する取引をピックアップします。
どの帳簿・書類をどの方式で電子保存するかを決める
電子取引として扱う取引が確定したら、それぞれのデータをどの方式で電子保存するかを検討します。電子取引を保存する際には、以下の2つの要件を満たす必要があります。
- 真実性の要件:保存されたデータが改ざんされていないこと
- 可視性の要件:保存されたデータを検索・表示できること
業務フローの見直しを行う
電子保存を適切に実施するには、業務フローの見直しも必要です。電子取引への対応が完了しても、当面は紙の種類を受け取る取引も残ると考えられます。電子データと紙が混在しても効率的に管理できるように、スキャナ保存などの対策も検討しておきましょう。電子帳簿保存の社内ルールを定め、適切に運用していくことが大切です。
まとめ
電子帳簿保存法では電子帳簿等保存やスキャナ保存は義務ではありませんが、電子取引のデータ保存は法人も個人事業主も対応が必須です。2023年中に対応が完了するように早めに準備を始め、この機会に業務効率化も実現させましょう。
(提供元:Mattrz![]() )
)
【関連リンク】
テレワークの現状と今後の課題 導入するメリットや問題点の解決方法を解説