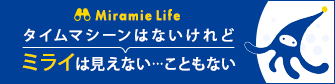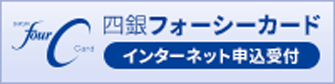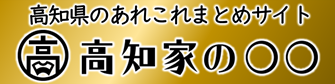![]() マネー
マネー
医療費控除について解説
出産にかかるお金は医療費控除で戻ってくる!
制度のかしこい活用法まとめ
2023/3/10

妊娠・出産は人生の一大イベント。出産が近づくにつれて、生まれてくる赤ちゃんに会える喜びは高まることでしょう。その反面で体調や出産における心配や、妊娠から出産までの数か月間で行う手続きを考えると、不安を感じる方もいらっしゃると思います。また、妊娠すると産休・育休によって収入が減ってしまうだけでなく、通院の機会が増えて医療費の負担が大きくなります。
2023年度から、出産育児一時金の支給額が50万円に引き上げられることになったものの、年々上がる出産費用。(※本記事は2023年2月時点の情報です)
妊婦健診費用や入院費用、マタニティ・ベビー用品など、妊娠から出産までにかかる費用は決して安くありません。出産後も何かとお金がかかるため、もらえるお金や戻ってくるお金があるなら余すところなく利用したいですよね。
このページでは、出産医療費控除とは何か、対象となるもの・ならないものの違いや、医療費控除を受けるための流れをまとめました。
育児に関する助成制度についても解説していますので、現在妊活中の方、育児中の方もぜひチェックしてみてください。
目次
■医療費控除とは
・医療費控除の対象になるもの・ならないもの
・医療費控除の上限金額
■出産や育児に関する助成制度とは
・出産育児一時金
・出産手当金
・高額療養費
・出産費貸付制度
・傷病手当金
■医療費控除には確定申告が必要
・還付金を受け取るまでの流れ
・過去5年分さかのぼって申告できる
■医療費控除を受ける為に準備するもの
■医療費控除の計算例
・出産一時金のみを受け取った場合
・高額医療費と医療保険が下りた場合
■医療費控除の注意点
医療費控除とは
医療費控除は、医療費が家計に与える負担を軽減するためにつくられた制度です。医療費が一定額を超えた場合、確定申告の際に医療費控除を申請すれば、所得控除という形でお金が戻ってくる、つまり「払い過ぎた税金」としてお金が戻ります。
妊娠・出産は病気ではないため健康保険の適用外ですが、出産費用は医療費控除の対象となります。また、不妊治療費なども医療費控除の対象となります。
- 納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
- その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります)。
引用:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
※ここでいう「生計を一にする」とは、同居や別居を問わず、日常生活で使うお金を共有している状態を指します。
医療費控除の対象になるもの・ならないもの
以下の費用が、医療費控除の対象となるものです。出産費用も含まれています。
- 通院や入院
- 医薬品
- 歯科費用
- 出産費用
ただし、出産費用であっても、下記のような費用は医療費控除の対象に含まれません。
- マッサージ師などによる施術費用
- 謝礼
- サプリメントなどの健康食品にかかる費用
- 自分都合で利用した差額ベッド代
基本的に治療目的ではないものは対象外となります。マタニティマッサージなどのリラクゼーションや妊婦さん向けのサプリメント代などは、控除の対象外となるため注意が必要です。
医療費控除の上限金額
医療費控除として認められる金額の算出方法には決まりがあり、算出した金額のうち、最高200万円が控除対象と決まっています。
算出方法は下記のとおりです。
- 実際に支払った医療費の合計額 - 保険金などで補てんされる金額 - 10万円(※注2)
※注2)ただし、その年の総所得金額等が200万円未満であれば、10万円ではなく総所得金額等の5%の金額を用いて計算します。
出産や育児に関する助成制度とは
深刻な少子化を食い止めようと、国や多くの自治体が出産や育児のための援助や手当の制度を設けており、もらえるお金や戻ってくるお金があるので、ぜひ活用したいところです。
中には、自治体独自の助成金や給付金制度を行っているところもあるので、お住まいの地域でどんな育児制度があるかはご自身で確認しておきましょう。ここでは、妊娠・出産時に受け取れる主な助成制度をまとめました。
出産育児一時金
入院・分娩にかかる高額な費用をまかなえるように、公的医療保険(健康保険、共済など)から分娩費の補助として給付される制度です。
支給を受けられる条件は、公的医療保険の加入者もしくはその家族(被扶養者)で、妊娠4ヶ月(85日)以上で出産すればもらえます。
現在、赤ちゃん1人につき国から出産育児一時金として42万円が支給されます。これは2023年4月から50万円に増額されることが決まっています。
多胎出産の場合、人数分もらうことができるので、双子の赤ちゃんなら2人分受け取ることが可能です。
ほとんどのケースが公的医療保険から病院に直接お金が支払われる「直接支払制度」を利用することが多く、支給分を超えた金額のみを病院に支払えば済むようになっています。
出産手当金
労働基準法に基づき、出産日以前の42日から産後56日までの期間で産休を取得できますが、産休の間は会社から給与が支払われない、もしくは支払われたとしても減額されてしまいます。このとき、加入している公的医療保険から支給されるお金が出産手当金です。
健康保険に加入していれば雇用形態を問わず受け取れるため、正社員やパート、アルバイトの人でも受け取ることができます。
ただし、受け取れる金額は、支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額(※注3)を平均した額によって異なるほか、産休後に職場復帰するか、出産で退職するかによっても違いがありますので、ご自身はいくらもらえるのかを事前に確認しておくことが大切です。
※注3)標準報酬月額とは、報酬月額を保険料額表の50等級分を基にした、ご自身が該当する金額のこと
高額療養費
妊娠・出産は病気ではないため、基本的に公的医療保険は適用されませんが、重症妊娠悪阻や切迫流産など、出産までに治療が必要なケースでは公的医療保険が適用されます。保険適用の医療費が1ヶ月の自己負担限度額を超えた場合は「高額療養費」の対象となり、医療費の助成を受けることができます。ただし、自己負担限度額は所得によって異なるため、こちらも確認が必要です。
出産費貸付制度
安心して出産を迎えられるように、出産育児一時金支給見込み額の8割を限度額として無利息で貸し付けてくれる制度です。出産予定日まで1ヶ月以内の方や、妊娠4ヶ月以上で病院に一時的な支払いが必要になった場合に受けられます。貸付金の返済は、出産育児一時金が給付された際に返済金に充てられます。
傷病手当金
急な入院やケガなどで働けなくなってしまった場合にもらえるのが傷病手当金です。 出産は病気ではないためもらえないと思っている人が多いですが、妊娠中のつわりや切迫流産、切迫早産の場合は傷病手当金がもらえます。
自宅療養の場合も医師の診断書があれば受け取りの対象となりますので、つわりがひどくて会社に出られず困っている際などは、まずかかりつけの病院やクリニックへ相談してみましょう。
医療費控除には確定申告が必要
会社勤めで年末調整を行っている人の場合、基本的に確定申告は必要ありませんが、医療費控除は年末調整では所得税額に反映されません。そのため、医療費控除を受けたいのであれば、ご自身で確定申告をする必要があります。
還付金を受け取るまでの流れ
確定申告をしてから還付金を受け取るまでの流れは以下のとおりです。
- 確定申告書を作成する
- 付表や計算書などを作成する
- 医療費控除の明細書とともに確定申告書を提出する
- 還付金を受け取る
確定申告は、税務署に行かなくてもe-Taxを利用すれば電子申告ができます。国税庁のホームページから確定申告書をダウンロードすることもできますし、マイナンバーカードを使えばスマホで簡単に申告ができて便利です。
還付金を受け取れる時期は明確に決まっているわけではなく、確定申告の方法やタイミングによって変わります。窓口や郵送で確定申告書を提出した場合は1ヶ月~2ヶ月程度、e-Taxを利用した場合は3週間ほどで還付されるケースが多いです。
会社員が年末調整以外に確定申告をする場合、ほとんどが「還付申告」となります。還付申告は1月1日から手続きできますので、なるべく早めに還付金を受け取りたい場合は、e-Taxを利用して、繁忙期の2~3月を避けた1月のうちに申告するとよいでしょう。
過去5年分さかのぼって申告できる
「医療費控除の存在を知らなかった」、「医療費控除の申告を忘れてしまった」という方も、まだ諦めるのは早いです。
医療費の領収書さえ取ってあれば、医療費控除は過去5年分までさかのぼって申告できます。はじめての妊娠・出産ですぐに育児が始まり、とにかく考える余裕がなかった、医療費控除について今理解した!という方も、妊娠中に通っていた病院の領収書を探してみてください。
医療費控除を受けるために準備するもの
医療費控除を受けるためには、以下6つの書類の準備が必要です。
- 確定申告書Aおよび医療費控除の明細書
- 医療費の領収書
- 医療費の明細書
- 健康保険の医療費通知
- 給与所得の源泉徴収票
- 本人確認書類
確定申告書にはAとBの2種類ありますが、会社員や公務員の還付申告の場合、多くが確定申告書Aを使用します。会社員で出産医療費控除を受けたい場合は、簡略版のAを利用しましょう。確定申告書には、収入金額や所得金額を書く欄のほかに「医療費控除」の欄が設けられています。源泉徴収票から給与収入や所得金額を転記したら、医療費の領収書をもとに「医療費控除の明細」を記載しましょう。
平成29年分の確定申告から、領収書の添付又は提示は必要なくなりましたが、医療費控除の明細書は添付する必要があります。また、確定申告の期限から5年間は、税務署より領収書の提示や提出を求められる場合があるので、捨てずに大切に保管しておきましょう。
医療費控除の計算例
医療費の還付金の計算は、所得税率によって異なります。
上の「医療費控除の要件と対象・上限金額とは」でも記しましたが、計算式は以下のとおりです。
■実際に支払った医療費の合計額 - 保険金などで補てんされる金額 - 10万円または所得金額の5%
所得合計額が200万円以上と仮定して、2パターンを計算してみましょう。
出産一時金のみを受け取った場合
- 出産にかかった費用:70万円
- 出産一時金:42万円
医療費控除額は以下のとおりです。
■出産費用(70万円) - 出産一時金(42万円) - 10万円=18万円
高額医療費と医療保険が下りた場合
- 帝王切開で出産した費用:65万円
- 出産一時金:42万円
- 高額療養費:10万円
- 医療保険:10万円
医療費控除額は以下の計算式になります。
■出産費用(65万円) - 保険金などで補てんされる金額(42万円 + 10万円 + 10万円)- 10万円=- 3万円
この場合、負担額が10万円を下回るため、医療費控除の対象外となってしまいます。 出産費用が高くても、保険が下りたために医療費控除の対象外となってしまうケースもあるため、注意が必要です。
医療費控除の注意点
医療費控除の特例措置のひとつに「セルフメディケーション税制」があります。セルフメディケーション税制とは、薬局やドラッグストア、コンビニなどで販売している「セルフメディケーション対象商品」を1年間に1万2千円以上購入した場合にも控除を受けられるというものですが、医療費控除とセルフメディケーションの併用はできません。出産医療費控除を申請する場合は、セルフメディケーションの申請はできないことを理解しておくようにしましょう。
また、出産の場合、健診が始まった時期と分娩の時期で、年をまたぐケースが多くあります。医療費控除の対象になる医療費は1月1日~12月31日の1年間で計算するため、年をまたぐ場合、医療費は2年に分けて計算しなくてはなりません。
もし年をまたいだ出産だとしたら、出産育児一時金は出産した年の医療費から差し引く必要があります。
医療費控除の仕組みを知って積極的に活用しよう
医療控除を受けるには確定申告が必要です。通院費用や医薬品の費用などかかった費用は、領収書をとっておいたり、家計簿に記録したりして、しっかりまとめておきましょう。また、医療費控除は、待っているだけではもらえません。出産や育児に関する助成金のことや、控除の対象となるものを必ずご自身で調べて、もらえるお金、戻ってくるお金をしっかり受け取りましょう。
四国銀行では、ほかにも経済やマネー・地域に密着した生活の情報などを発信しております。
ぜひ、いま話題になっている経済のことやお金に関する情報などの、疑問解決にお役立てください。
(提供元:全研本社)
【関連リンク】
副業で確定申告する金額の基準は?税金の種類や注意すべき点をチェック!