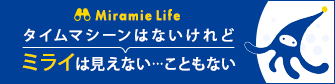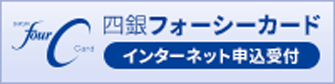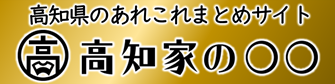![]() 経済
経済
2023年10月1日から開始
インボイス制度とはどんな制度?
仕組みや登録方法、注意点などを徹底解説
2023/9/28

消費税の納税に関わるインボイス制度が、2023年10月から導入されます。インボイス制度のメリットを活用しながらデメリットへ対処するために、理解を深めたうえで検討することが大切です。この記事では、インボイス制度の仕組みや登録方法、注意点について解説します。
インボイス制度とは

まずは、インボイス制度の仕組みや登録方法、影響を受ける業種について解説します。
インボイス制度の仕組み
インボイス制度は2023年10月から開始される消費税の仕入税額控除の方式で、「適格請求書等保存方式」とも呼ばれます。消費税を納税する事業者が計算の際、売り上げの消費税から仕入れ時の消費税を差し引く制度が仕入税額控除です。消費税率が明記されたインボイス(適格請求書)によって、仕入による購入額と消費税額を明確に伝えられます。申告すべき消費税は2種類あり、それぞれの税率でのインボイス作成が必要です。
消費税率による納税する消費税額の計算
● 標準税率10%売上1100円(内消費税100円)ー仕入550円(内消費税50円)=利益550円(納税する消費税額50円)
● 軽減税率8%
売上1080円(内消費税80円) ー仕入540円(内消費税40円)=利益540円(納税する消費税額40円)
また、仕入税額控除を受けるためには、販売側と仕入側の双方のインボイス制度への登録が必要になります。
インボイス制度の登録方法
インボイス制度に登録するためには、適格請求書発行事業者の登録申請書を管轄の税務署に提出します。国税庁のHPからダウンロードした申請書に記入して郵送する方法だけでなく、e-Taxではオンライン申請が可能です。
税務署への申請後、登録番号の交付を受けます。インボイス制度への登録が完了したら、事業の取引先に登録番号とインボイスの受領方法を伝えましょう。
インボイス制度の影響を受ける業種
インボイス制度は仕入れの際に消費税が発生する飲食業や小売店、個人事業主といった業種が影響を受けやすいです。
すでに課税事業者である売上1000万円以上の企業より、1000万円以下の免税事業者の方が受ける影響は強くなります。消費税の免税事業者がインボイス制度へ登録すると、課税事業者にならなければなりません。免税事業者にとって、消費税の税率分は売上となっています。そのため、免税事業者がインボイス制度に登録して課税事業者になると、消費税の税率分の売上が減ってしまうのです。
売上1000万円以上の課税事業者のメリットとデメリット
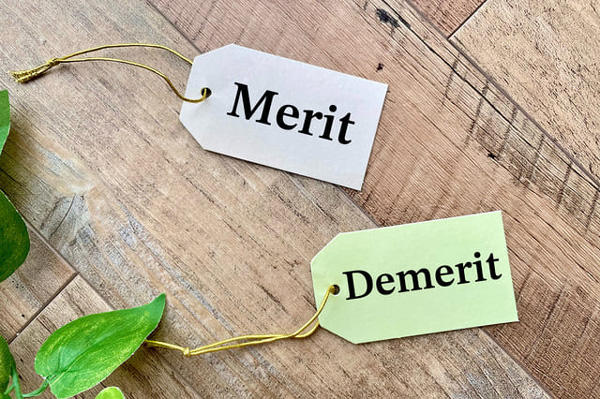
インボイス制度は売上が1000万円以上の課税事業者と以下の免税事業者によって、メリットとデメリットが異なります。
最初に、売上1000万円以上の課税事業者のメリットとデメリットを確認していきましょう。
メリット
売上1000万円以上の課税事業者のメリットは、以下の2つです。
消費税率を正確に記載できる
インボイス制度では標準税率10%、軽減税率8%のそれぞれでインボイスを作成するため、消費税率を正確に記載できます。2019年10月の消費税率引き上げにともなって開始された軽減税率により、税率を分けて管理する必要が生じました。インボイス制度では請求書のフォーマットを分けて作成し、購入額と消費税額が明記されるため、正確に管理しやすくなるのです。
業務を効率化できる
インボイス制度の開始にあわせて電子インボイスを導入すると、業務を効率化できます。オンラインで手続きが完了できると、紙面で請求書を作成して郵送する手間がなくなり作業が簡単です。
デメリット
売上1000万円以上の課税事業者のデメリットは、以下の2つです。
会計業務の手間が増える
インボイス制度の開始直後は、新しい請求書のフォーマットを作成したり、インボイスを管理したりすることの手間が発生します。
ただし、フォーマットを作成して管理する仕組みが整えば従来の方法より手間を省けるため、一時的なデメリットとなるでしょう。
免税事業者との取引では仕入税額控除ができない
売上1000万円以上の事業者が免税事業者と取引すると、仕入にかかる消費税を控除できないため売上が下がります。売上1000万円以上の事業者にとって、仕入れの消費税が控除できないのはデメリットとなります。よって、インボイス制度に登録して課税事業者となった事業者を、取引先に選ぶ可能性が増すでしょう。
売上1000万円以下の免税事業者のメリットとデメリット

売上1000万円以下の場合、免税事業者のまま継続するか、インボイス制度に登録して課税事業者となるか選択します。
メリット
売上1000万円以下の免税事業者のメリットは、以下のとおりです。
登録すると取引きで有利になる可能性がある
課税事業者が免税事業者と取引すると仕入税額控除が適用されず、実質的な売上が下がるため、取引相手が、免税事業者であるか否かが、課税事業者にとって重要になってきます。そのため、売上1000万円以下だった事業者がインボイス制度に登録して課税事業者になると、取引先の企業から選ばれやすくなる可能性があります。
同じ商品を仕入れる場合、免税事業者より課税事業者が選ばれやすくなる可能性が高いため、登録すると取引きで有利になるかもしれません。既存の取引相手と継続して取引きできる関係につながるでしょう。
また、インボイス制度の開始で同業他社が免税事業者を継続し、自社が課税事業者となった場合、新規案件を獲得しやすくなる可能性があります。課税事業者になることで新規案件を獲得できると事業規模拡大を図れるでしょう。
デメリット
売上1000万円以下の免税事業者のデメリットについて解説します。
納税額が増えて利益が減る
インボイス制度に登録し、課税事業者になった場合、消費税を納税する必要があるため、税率分の売上が下がります。免税事業者には不要だった消費税で、売上の8%や10%が課税されるのは大きなデメリットといえるでしょう。利益が減ることへの対策には、課税事業者として新たな取引先の開拓が効果的であると考えられます。課税事業者は免税事業者と比較して新規開拓が行いやすくなり、売上の総額が高くなれば利益の底上げができます。
また、インボイス制度の開始から6年間は、一定割合を仕入税額控除できる経過措置があります。最初の3年間は80%、次の3年間は50%が仕入税額控除可能です。
免税事業者を継続すると仕入税額控除が適用できないため、課税事業者の取引先から選ばれにくくなる可能性があります。取引先の意向を把握したうえでインボイス制度への登録を検討しましょう。
インボイス制度の注意点

インボイス制度に対応するための注意点について解説します。
経理業務を全般的に見直す
インボイス制度に登録すると請求書のフォーマットや取引先とのやり取りが変わるため、経理業務を全般的に見直す必要があります。インボイスの発行だけでなく写しの保存など、義務化される業務を確認して、経理業務を整理しておくことが大切です。
請求書のフォーマットを変更する
インボイス制度では従来の請求書では不要だった、以下の項目の記載が追加されます。
インボイス制度で記載すべき項目
● 発行事業者の氏名、または、名称
● 発行事業者のインボイス制度の登録番号
● 取引年月日
● 交付先の事業者(取引先)の氏名、または、名称
● 取引の内容(軽減税率の対象品目など)
● 税率で区分して算出した対価の金額と適用税率
● 税率ごとに区分した消費税の税額
必要な項目に抜けもれがないように注意して、請求書のフォーマットを作成しておきましょう。
まとめ
インボイス制度は10%と8%の2種類が混在する消費税の正確な納税額の算出、また益税※をなくすことで消費税納税における不公平をなくすのが導入の目的となっています。インボイス制度のメリットを活用すると、業務を効率化できたり事業規模を拡大できたりする可能性があります。また、デメリットを理解したうえで対処法を検討し、事前に対策しておくことも大切です。インボイス制度の仕組みや登録方法、注意点の参考にしてみてください。
※消費者が事業者に支払った消費税が、納税免除・軽減により合法的に事業者の利益になること
(提供元:Mattrz![]() )
)
【関連リンク】
「電子帳簿保存法」とは?改正概要や対応ポイント、対象者をわかりやすく説明!