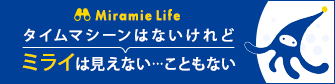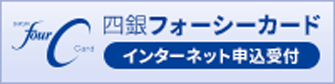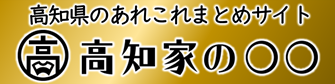![]() 経済
経済
子育てしやすい社会に向けて
子育て支援には何がある?新制度により拡充した児童手当ほか、各種支援を解説
2024/12/6

少子化が進むなか、保護者が安心して子育てができるよう国や行政がさまざまな子育て支援をおこなっています。支援制度の内容を正しく理解して利用することで、家庭への負担が軽減できます。 本記事では新制度により拡充された児童手当をはじめ、助成制度や教育の無償化など知っておきたい子育て支援には何があるのか、一覧を紹介します。
子育て支援制度とは?

子育て支援制度は、子育てをしている家庭をサポートするために、国や地方自治体が提供するさまざまな支援施策のことです。経済的な支援のほか、育児に関するサービスの提供が含まれています。
経済的支援は児童手当や教育に掛かる費用負担など、育児に関する出費における家庭の負担を軽減するためのサポートがメインです。教育に掛かる費用負担では、学費の支援だけでなく、学校生活に必要な費用の支援もあります。
育児サービスの提供としては保育園や認可外保育施設への助成、学校施設の充実などがあり、保護者が育児をしながら仕事を続けやすい環境や子どもが安心して学べる環境づくりを提供しています。
子ども支援制度の財源は?
子ども支援制度に捻出される費用は、現在は国税、地方税、事業主拠出金などで賄っていますが、2026年より「子ども・子育て支援金」として医療保険料と合わせた徴収が予定されています。「子ども・子育て支援金」は、現在育児をしていない人と育児が終わった人だけでなく、育児をしている人も支払う必要があります。
少子化や人口減少は日本全体の問題であり、今後の日本を考えるうえで非常に重要な課題です。「自分は育児をしていないから関係ない」と考えるのではなく、日本の社会システムを継続するために、国民すべてが、「子育てをしやすい社会づくり」に参加する必要があります。その一環として、国民が医療保険料とともに子育て支援に必要な費用を負担するという仕組みが考えられています。
利用できる子育て支援制度には何がある?

現時点で利用できる子育て支援制度は何があるのかを、解説します。以下の制度だけでなく、今後ライフステージに応じてさまざまな施策も予定されています。
子育て支援に関する制度は毎年拡充されており、最新の変更や更新を見逃さないよう、常に情報をキャッチすることも大切です。
ここではまず、子育て支援制度のなかから児童手当、育児休業給付、教育・保育の無償化について解説します。
児童手当
児童手当は、子育てに必要な各家庭の負担を軽減するために支給される給付金です。これまでは所得制限があり、中学生以下の子どもが対象で、年3回の支給でした。
2024年10月からはさらに充実した支援内容にするために、児童手当の内容が大幅に改良されました。まず所得制限が撤廃され、所得にかかわらず、すべての子育て世帯が全額受け取れることになりました。さらに、対象が高校生にまで引き上げられました。また、第三子以降の支給額は3万円に増額され、多子世帯はさらに手厚い支援を受けられる制度に見直されました。
支給回数は年3回から年6回に増え、より活用の計画が立てやすくなったのもポイントです。
育児休業給付
育児休業給付には、出生時育児休業給付金と育児休業給付金があります。どちらも育児休業を開始する日より前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あること、ない場合は就業した時間数が80時間以上あることが条件です。
出生時育児休業給付金は子どもの出生後8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間(28日)以内の期間を定めて産後パパ育休を取得し、一定の要件を満たすと受け取れます。育児休業給付金は、雇用保険に加入している方が1歳未満の子どもの育児のために休業する際に支給される給付金です。
さらに詳しく知りたい方は、以下のリンクを確認してみてください。
幼児教育・保育の無償化
幼児教育・保育の無償化は、急速な少子化の進行、また幼児期の教育や保育の重要性から、少子化対策の一環として子育て世帯の教育にかかる費用の負担軽減を図ることを目的としています。若い世代が、「子育てや教育にお金がかかる」という理由で、子どもを持たない、また理想とする子供の数を持たないという問題の解決策として、2019年にスタートした制度です。
3歳から5歳までのすべての子どもたち、市町村民税非課税世帯の0歳から2歳の子どもたちの利用料が無償化されます。地域によって変動するものの、例として以下のような施設を利用することができます。
無償で利用できる施設・事業
- 幼稚園
- 保育所
- 認定こども園
- 企業主導型保育事業
- 幼稚園の預かり保育
- 認可外保育施設
- 一時預かり事業
- 病児保育事業
- ファミリー・サポート・センター事業
| 制度名 | 概要 |
| 自立支援医療(育成医療) | 18歳未満の子どもに対し、指定医療機関において障害を軽減、回復させる治療をおこなう際に医療費の一部を公費で負担する制度 リンク:厚生労働省 自立支援医療 |
| 子ども医療費助成制度 | 子どもの病気やけがに対して医療費の自己負担額の一部を支援する制度 リンク:厚生労働省 各自治体の「医療費助成」についての取組 |
| 子育て支援パスポート | 国、自治体、企業、店舗が連携して子育て世帯を支援する事業。発行されたパスポートを提示することで割引や優待を受けられる。 リンク:こども家庭庁 子育て支援パスポート事業 |
| 就学援助制度 | 経済的な理由で義務教育を受けさせることが困難な家庭を対象に、学校で必要な費用の一部を市町村が支援する制度 リンク:文部科学省 就学援助制度について |
| 児童扶養手当 | 離婚や死別などを理由にひとり親となった世帯に対して給付される手当。ひとり親世帯の生活の安定と自立の促進と児童の福祉の増進を目的としている。 リンク:子ども家庭庁 児童扶養手当について |
| 高等学校等就学支援金制度 | 国公私立を問わず、高等学校に通う年収約910万円未満の世帯に対して授業料の一部を支援する制度 リンク:文部科学省 高等学校等就学支援金制度 |
| 高校生等奨学給付金 | 低所得世帯を対象に、高校生の授業料以外の教育費を支援する制度 リンク:文部科学省 高校生等奨学給付金 |
| 奨学金 | 経済的な理由で進学が困難な学生を対象に、学費や生活費を支援する制度。無利子または低利子で借りられる貸付型と、返済義務のない給付型がある。 リンク:日本学生支援機構 奨学金 |
出産費用が保険適用になるのはいつ?

出産費用の保険適用について、2026年度を目処に検討が進められています。2025年の通常国会で法改定がおこなわれ、2025年末の診療報酬改定によって診療報酬が設定されるというスケジュールが組まれています。
現在、出産費用は保険適用外となっており、高額な費用がかかることも少子化の原因の一つとして懸念されています。出産にかかる費用は地域によって異なるものの、平均して50万円程度かかっています。地域によって20万円以上の差が生まれていることも深刻な問題です。
出産費用が保険適用になることで出産費用の大幅な負担軽減につながることが期待されています。
まとめ
経済的な負担が大きい育児を支援する助成金やサービスを一覧で紹介しました。国や自治体、企業による多様な支援制度を活用することで、日々の生活や教育における負担を軽減することができます。
紹介した支援制度を上手に活用することで、より豊かな子育て生活にお役立てください。
2級FP技能士
広告代理店勤務を経て、フリーライターとして6年以上活動。自身の投資経験をきっかけにFP資格を取得。投資・金融・不動産・ビジネス関連の記事を多数執筆。現在はフリーランスの働き方・生き方に関する情報も発信中。
(提供元:Mattrz![]() )
)
出産にかかるお金は医療費控除で戻ってくる!制度のかしこい活用法まとめ
宝くじの当選確率はどのくらい? 当たりやすくする秘訣などを徹底解説!