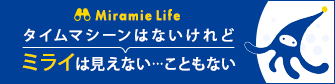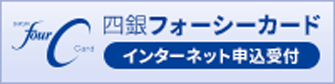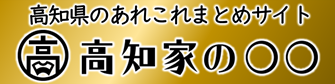![]() 経済
経済
Z世代が消費で求める価値とは?
イミ消費とは?Z世代を中心に広がりを見せる「イマ」の消費傾向をわかりやすく解説
2025/4/18

「イミ消費」とは、"意味"や"共感"を重視する消費行動です。とくにZ世代の消費傾向として増加しており、近年のマーケティングにおいても重要になってきています。本記事では、イミ消費とは何なのかを解説し、具体例などを紹介します。
イミ消費とは?

イミ消費とは、商品やサービスを購入する際に、単なる機能や価格だけでなく、「自分の価値観や信念」に基づいて選択する消費行動を指します。これは従来の消費行動として挙げられていた「モノ消費」や「コト消費」とは異なり、商品や体験そのものよりも、その背景にあるストーリーや理念に共感できたり、価値を感じることができるかが重視される点が特徴です。
自分自身の価値観を反映する消費の仕方
イミ消費の消費行動の一つとして挙げられるもので、「自分自身の価値観やライフスタイルと一致する」商品を選ぶことを重視するという考え方があります。例えば、ヴィーガンの方が動物性原料を使わない食品やコスメを選ぶ、ミニマリストが必要最小限の持ち物だけを購入する、などの行動が挙げられます。
単なる流行ではなく、個々の価値観が反映される点が特徴で、「消費を通じて自己表現を行う」という手段としての行動ともいえるでしょう。
一時的な消費ではなく満足度の高い消費の仕方
イミ消費には、「長期的な満足度を求める」という消費行動もあります。例えば、使い捨ての商品ではなく、長く使える高品質なアイテムを選ぶ、持続可能な素材で作られた衣服を販売するファッションブランドを好むといった選択がこのようなイミ消費にあたります。
このような消費行動は、購入したものが長期的に見て自分の生活や価値観にどう影響を与えるかを重視するもので、購入後の満足度が高い傾向があります。
歴史・伝統・社会・環境を守る消費の仕方
イミ消費には、「社会的、文化的な側面を重視する」ものもあります。例えば、伝統工芸品や地元の職人が作った商品を選ぶことで文化継承に貢献する、地元産の食材を購入することで地域経済を支える、といった行動が該当します。
また、環境に配慮したエコ製品を選んで持続可能な社会作りに貢献することも、イミ消費の一つといえるでしょう。
共感に基づいた消費の仕方

近年、Z世代を中心に「"共感"に基づく消費行動」が広がっています。例えば、「推し活」と呼ばれる好きなアイドルやアーティストの商品を購入する行動や、特定のブランドやクリエイターを応援するために商品を購入する行動などが挙げられます。
これらは、単に商品を所有することが目的ではなく、共感から応援したいという気持ちが生まれたり、作者やキャラクターとのつながりやそれによる自己表現が消費行動に直結している点が特徴です。
イミ消費が生まれた背景とZ世代で広まった背景
2010年代以降、SNSの普及や価値観の多様化により、「イミ消費」が注目されるようになりました。特にZ世代は、環境問題や社会貢献、自己表現に敏感であり、消費行動と結びつける傾向にあると言えるでしょう。
また、コロナ禍以降、個人の価値観や自己投資を重視する消費行動が加速し、推し活やクラウドファンディングなどを通じたイミ消費も拡大しました。加えて、健康志向の高まりもこの動向に影響を与え、健康に良いとされる商品やサービスへの関心が強まっています。
自身の心身の健康や精神的な充足感を意識した選択が、自己投資の一環としても重視されるようになっています。
イミ消費と他の消費行動との違い

イミ消費は、従来のモノ消費やコト消費と異なります。
各年代の時代背景からどのような消費行動が生まれたのか見ていきましょう。
1950後半~90年代はモノ消費
1950年~1970年代の高度経済成長期の日本では、物質的な豊かさを求める「モノ消費」が主流でした。テレビや自動車、家電などが次々と普及し、生活を便利にするモノを消費する時代でした。
その後、バブル経済期といわれる1980年~1990年代は、高級車やブランド品の所有がステータスとなり、商品を手に入れることが成功や幸せという価値観が広がりました。
1990年代後半~2000年代はコト消費
バブル崩壊後、人々の関心は「モノ」から「コト」へと移行しました。旅行やイベント、スポーツ観戦、ライブといった"体験"に価値を見出すコト消費が主流となり、モノ消費とは違い経験の充実が重視されるようになりました。
SNSの発展により「映える体験」や「シェアできる体験」が重視され、インスタ映えする旅行先やイベントが人気を集めたのも、コト消費の一環です。
そして前述のとおり、2010年代頃に「イミ消費」という消費行動が注目されはじめました。消費の価値は「モノを持つ」ことから「体験するコト」へ、そして「イミを感じる」ことへシフトしています。共感や社会性といった"意味"が消費行動へ反映される時代となりました。
イミ消費の具体例
イミ消費とは具体的にどのようなものなのか、詳しい例を見てみましょう。
売上の一部が募金される商品を選ぶ
売上の一部が社会貢献活動に寄付される商品を選ぶのもイミ消費の一例です。例えば、チャリティTシャツや特定の団体と提携した商品を購入することで、その収益の一部が直接支援活動に使われます。
消費者は購入を通じて社会貢献に参加でき、支援活動を直接的にサポートすることができます。
フェアトレードの商品を選ぶ

フェアトレード商品を選ぶことも、イミ消費の代表的な例です。フェアトレードとは、発展途上国の生産者が適正な価格で取引できるようにする制度で、特にコーヒーやチョコレート、紅茶などが多く取り扱われています。
フェアトレード認証を受けたコーヒーを購入することで農家の労働環境や収入が改善されるなど、共感や社会貢献の気持ちが消費行動につながっています。
リサイクルやアップサイクルされた商品を選ぶ
環境意識の高まりとともに、リサイクル素材を使用した商品を選ぶイミ消費への関心も高まっています。例えば、ペットボトルを再利用したアパレル商品や、アップサイクルされた家具・雑貨などは、環境負荷の軽減に貢献する手段です。
消費者はこれらを購入することで環境問題への意識を示すとともに、アップサイクルの商品においては、意味があるうえに、ユニークで自分らしいなど、自身の個性とリンクする選択としての消費行動にもつながっています。
※アップサイクルとは、本来は廃棄される素材に新たな要素やデザイン性を加えることで、資源の有効活用と環境への配慮を両立させる手法のこと。
伝統的な技術が使われた商品を選ぶ
日本の伝統工芸品や地域の特産品を購入することも、イミ消費の一環として広がっています。例えば、和紙や陶器、漆器などの伝統工芸品を購入することで、職人の技術や文化の継承を支援できます。
消費者は地域の工芸品を選ぶことで、地元の職人を支援し、地域経済に貢献できるのです。
自分が好きな対象に関する商品をえらぶ
推し活やエモ消費も、イミ消費の一部として定着しています。
推し活として好きなアーティストやクリエイターの商品を購入することで、活動の支援ができます。また、オリジナルグッズの購入やクラウドファンディングへの参加は、単なる消費行動ではなく、自己表現や価値観の反映としての役割を持っています。
エモ消費とは、「感情が動くから選ぶ」消費行動を指します。単なる商品やサービスの機能・価値ではなく、個々がそれぞれ抱く"ときめき"や"懐かしさ"などが動機となる消費スタイルです。
まとめ
時代背景とともに消費行動の変化が見られます。イミ消費は自分の価値観や"共感""応援"などを反映し、時には社会や環境保全に貢献するなど、「意味を感じるからこそ買う」という新しい消費スタイルです。
特にZ世代を中心に広がり、SNSを通じた自分らしさの発信や共感型の消費行動が注目されています。今後も、個人の価値観に基づいた消費行動がより一層進化していくでしょう。また、時代の変遷で新しい消費行動が生まれるかもしれません。
あなたのイミある消費は何でしょう?インフレが進む昨今、自身の消費行動を意味あるものにしてみてはいかがでしょうか?
2級FP技能士
広告代理店勤務を経て、フリーライターとして6年以上活動。自身の投資経験をきっかけにFP資格を取得。投資・金融・不動産・ビジネス関連の記事を多数執筆。現在はフリーランスの働き方・生き方に関する情報も発信中。
(提供元:Mattrz![]() )
)