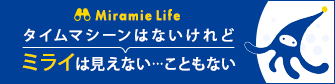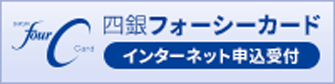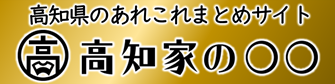![]() 経済
経済
今後の働き方のご参考に
106万円の壁とは?メリットやデメリット、撤廃された場合の影響などを解説
2025/8/22

「働く時間を増やしたいけれど、106万円を超えると手取りが減ってしまう...」
年収106万円を境に社会保険料が発生し、手取り額が変わるこの仕組みは、働き方の選択に大きな影響を与えています。現在、この制度の撤廃に向けた議論も進んでいます。この記事では「106万円の壁」の基本的な仕組みやメリット・デメリット、撤廃された場合の影響について解説します。
「106万円の壁」の基本的な仕組み

社会保険への加入基準となる年収106万円。この金額を超えると社会保険料が発生し、手取り額が減少することから「106万円の壁」と呼ばれています。まずは、この制度の基本的な仕組みを解説します。
社会保険制度とは
社会保険は、病気やケガ、出産、死亡、業務上の災害、失業、老後の生活など人生におけるさまざまな場面で必要となる保障を提供する公的な保険制度です。加入者は保険料を納めることで、必要な時に必要な給付を受けることができます。
社会保険は以下、4種類に分けられます。
- 健康保険:医療費の保障
- 厚生年金保険:老後の生活保障
- 労災保険:業務上の災害や事故などの補償
- 雇用保険:失業時の保障
このうち、「106万円の壁」に関係するのは、健康保険と厚生年金保険の2つです。
労災保険は、保険料を事業主が全額負担するため、従業員に費用の負担はなく、また雇用保険は月収に対して一定の割合で保険料がかかる仕組みのため、「年収の壁」とは直接関係しません。
一方、健康保険と厚生年金保険は、月収に応じて「標準報酬月額」が決まり、それに基づいて保険料が算出される仕組みになっているため、年収106万円以上あるかどうかが関係してくるのです。
社会保険への加入要件
社会保険への加入義務が生じるのは、以下のすべての要件を満たす場合です。
社会保険の加入要件
- 勤務先の従業員数が常時51人以上
※企業規模の要件は、従来の「従業員101人以上」から、2024年10月より「51人以上」に拡大されました。 - 月収8.8万円以上(年収106万円以上)
- 所定労働時間が週20時間以上
- 雇用期間が2ヶ月を超える見込み
- 学生ではない
社会保険加入基準となる月収の計算方法
社会保険への加入基準となる月収8.8万円以上(年収106万円以上)は基本給だけでなく、通勤手当など定額で支給される各種手当も含まれた総支給額のことを指します。
【月収に含まれるもの】
・基本給(毎月の給与)
・通勤手当
・家族手当
など、定額で支給される諸手当
【月収に含まれないもの】
・賞与(年間3回以下)
・病気見舞い金・結婚祝
など、支給額が変動する手当や臨時的な手当
勤務先や働き方によっては、「予期せず社会保険の対象になってしまった」というケースもあるので、ご自身の月収の内訳を把握しておくことが大切です。
106万円の前後での社会保険料の違い
年収106万円以内の場合、社会保険料は発生しないため、税金(所得税と住民税)を除いた金額が手取りになります。一方、年収106万円を超えると社会保険料が発生して、保険料を差し引かれた分だけ手取り額が少なくなります。
具体的な例として、年収96万円(月収8万円)と年収108万円(月収9万円)の場合で、社会保険料がどのように違うのか比較してみましょう。
※社会保険料は全国健康保険協会(協会けんぽ)東京支部の金額(健康保険料は介護保険第2号被保険者に該当しない場合)
全国健康保険協会(協会けんぽ)令和7年度保険料額表(令和7年3月分~)
| 月額給与 | 健康保険 | 厚生年金保険 | 社会保険料合計 | 給与-社会保険料 |
| 80,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 80,000円-0円=80,000円 |
| 90,000円 | 4,360円 | 8,052円 | 12,412円 | 90,000円-12,412円=77,588円 |
このように、社会保険料が発生することで、月収が1万円増えても手取り額は減少してしまうのです。
106万円の壁は撤廃する方向で調整中(2025年7月現在)

現在、社会保険の加入条件のうち「106万円の壁」となっている賃金要件について、撤廃に向けた検討が進められています。
撤廃が検討される背景
撤廃が検討される背景には、現行制度が抱えるさまざまな問題があります。106万円を超えると手取り額が減少するため、多くの労働者が収入を抑える「働き控え」を行っています。また、企業側も負担する社会保険料を抑えるために、労働者の働き方を制限するケースも見られます。このような状況は人手不足を深刻化させ、さらには労働者が十分な社会保障を受けられないという事態も招いています。
106万円の壁を撤廃することにより働き控えや労働制限を減らし、公平な社会保障を受けながら多様な働き方を実現できる可能性があります。企業にとっては、106万円の壁で労働時間や雇用を調整することなく、必要な人材を確保することにつながります。
また、社会保険料の納付額が増えると、人口減少や少子高齢化のなかでも、社会保険制度の安定化が期待できます。
106万円の壁が撤廃された場合の変化

ここからは、106万円の壁が撤廃された場合の変化について解説します。
多様な働き方の選択肢が増える
これまで「106万円の壁」を意識して仕事を制限していた人は、収入を気にせず労働時間を増やすなど、より柔軟な働き方が可能になります。
また、社会保険への加入により、必要な社会保障を受けられるようになり、長期的なキャリア形成も考えやすくなります。
賃金要件は撤廃、労働時間要件は継続
賃金用件が撤廃された後も週20時間以上という労働時間要件は変更されないため、社会保険料の負担を避けたい場合は、週の労働時間で調整する必要があります。特に共働き世帯のパートタイマーや副業ワーカーの中には、この時間条件をもとに働き方を選択するケースが考えられます。
106万円の壁の撤廃のメリット・デメリット

ここからは、106万円の壁の撤廃による影響について、働く個人と企業それぞれの立場から、具体的なメリット・デメリットを見ていきましょう。
個人のメリット・デメリット
106万円の壁撤廃によって、社会保険に加入するとより充実した社会保障を受けられるようになります。例えば、健康保険では病気やケガによる休業を保障する傷病手当金の対象者になることに加え、出産のために会社を休んだ場合は、出産手当金として給与の3分の2が受け取れます。
一方で、社会保険料の負担が発生するため、手取り額が減少することになります。
企業のメリット・デメリット
働き手の収入制限がなくなることで、長時間勤務可能な人材の安定的な確保や業務改善が期待できます。
ただし、社会保険の対象者が増えることで、企業側は新たな対応が必要となります。加入手続きの事務作業が増え、従業員への周知や説明も必要です。さらに、社会保険料の会社負担も増加するため、人件費の見直しなども検討が必要になるでしょう。
ほかの年収の壁との違い
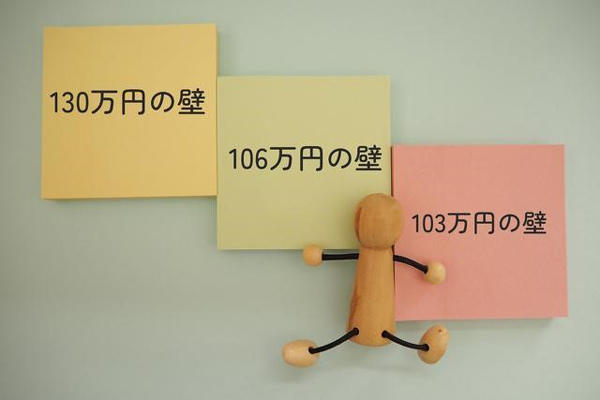
ここまで「106万円の壁」について解説してきましたが、収入に応じて発生する税金や社会保険料には、ほかにもいくつか重要な基準があります。収入が増えると、社会保険の扶養から外れたり、税金(住民税、所得税)が発生するタイミングがそれぞれ異なったりします。そこで、夫が世帯主(扶養者)、妻が被扶養者である世帯の場合を例に、具体的に見てみましょう。
103万円の壁
103万円は税金(住民税、所得税)が発生する基準年収です。この例で言うと、被扶養者である妻の年収が100万円を超えると住民税が発生し、103万円を超えると所得税も課税されます。ただし、この基準は税金に関するもので、社会保険料は扶養者の夫のみが支払います。
130万円の壁
130万円を超えると、被扶養者である妻も社会保険への加入が必要となります。具体的には、健康保険と厚生年金保険(個人事業主の場合は、国民健康保険と国民年金)の保険料を自身で負担することになります。
そのほかの年収の壁
年収の壁には税金と社会保険の違いがあり、それぞれの要件を整理して理解することが大切です。以下の表は、夫を世帯主としたときの妻の年収による税金と社会保険料の関係をまとめました。
| 妻の年収 | 妻の住民税の支払い | 妻の社会保険の支払い | 妻の所得税の支払い | 夫の所得税控除 |
| 100万円未満 | なし | なし | なし | 控除適用 |
| 100万〜103万円未満 | あり | なし | なし | 控除適用 |
| 103万〜106万円未満 | あり | なし | あり | 控除適用 |
| 106万〜130万円未満 | あり | あり(条件による) | あり | 控除適用 |
| 130万〜150万円未満 | あり | あり | あり | 控除適用 |
| 150万〜201万6,000円未満 | あり | あり | あり | 控除適用 |
| 201万6,000円以上 | あり | あり | あり | なし |
※妻の年収が150万円以上になると、段階的に夫の所得税の控除額が減額します。
まとめ
「106万円の壁」の撤廃に向けた検討が進められており、社会保険の加入要件から収入による制限がなくなる可能性が出てきました。これは、私たちの働き方を見直す機会と捉えることができます。
ただし、社会保険料の負担により手取り額が減ることや、労働時間の調整が必要になったりする可能性があるため、状況に応じた働き方の検討が必要となります。この記事で解説した制度の内容や、撤廃に伴う影響についての理解を深め、今後の働き方を考える参考にしてみてください。
FP技能士2級、AFP
ライフとキャリアを総合した視点で、人生設計をマンツーマンでサポート。日々の家計管理から、数十年先に向けた資産設計まで実行支援しています。
(提供元:Mattrz![]() )
)