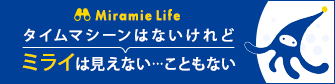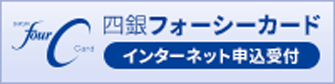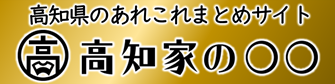![]() マネー
マネー
2026年酒税法改正
酒税一本化とは?改正の背景や目的、ビール・発泡酒への影響を知っておこう
2025/11/5

スーパーやコンビニで『お疲れ様の一杯』を買うとき「今日はビール?それとも値段を抑えて発泡酒?」と財布と相談した経験、きっと皆さんにもあるのではないでしょうか。
この価格差には、実は複雑な酒税制度が関わっています。
従来、ビールや発泡酒、第三のビールやワインなどは、お酒の種類や原材料によって細かく異なる税率がかけられてきました。消費者には分かりにくく、メーカーにとっても事務負担や商品開発を複雑にする要因となっていました。こうした状況を改善するために導入されたのが「酒税一本化」です。
ビール類の分類制度

ビール・発泡酒・第三のビールは、主に原料や製法、麦芽の割合の違いで分類されます。ビールは麦芽の割合が高く、ホップや酵母の使用についても一定の基準を満たす必要があります。一方、発泡酒は麦芽の割合が低く、第三のビールはコーンや大豆など麦以外の原料を使うことで、価格を抑えています。
こうした違いにより「ビールは高いが、発泡酒や第三のビールは安い」という価格差が生まれ、消費者は価格を重視して商品を選ぶ傾向が強まりました。その一方で、メーカーは税制に合わせた商品作りを進めざるを得ず、酒税制度はますます複雑化していったのです。
酒税一本化とは?

ここからは、酒税一本化の概要や目的、今後の価格への影響について詳しく解説します。
酒税一本化の概要
酒税一本化とは、これまでビール・発泡酒・第三のビールなどで異なっていた税率を段階的に統一する制度のことです。この一本化を実現するために酒税法の改正が行われ、2023年10月から段階的に税率統一が始まりました。
そして、2026年10月1日に1キロリットルあたり15.5万円で完全統一され、長年続いてきた複雑な税率制度が終了する予定です。この税率統一により、従来の税率差によって生じていた市場の偏りが小さくなり、さらに、複雑だった酒類の分類や課税方法の簡素化により、メーカーの事務負担軽減と行政の課税管理効率化が期待されています。
税率改正による値段の変化
酒税一本化により、従来はビールが高税率、発泡酒や第三のビールが低税率だったため生じていた価格差が縮まります。ビールの価格はやや下がり、発泡酒や第三のビールの価格は上がる可能性が高いと考えられます。
酒税一本化が与える影響

ここからは、酒税一本化が与える影響を詳しく解説します。
製造現場への影響(商品開発や経営戦略)
酒税一本化は、メーカーの経営戦略や商品開発に大きな影響を及ぼすと考えられます。低価格帯の発泡酒や第三のビールは従来の優位性を失い、品質や差別化で勝負しなければなりません。メーカーは商品の価値を高めるため、味や原料配合の見直し、ラインナップの再編、パッケージ戦略などによって差別化を図る必要があるでしょう。
消費者の選び方・価格の変化
統一税率により、消費者は価格差だけでなく、味やブランド、飲みやすさを重視して商品を選ぶようになるでしょう。これまで「安いから」という理由で人気を集めていた発泡酒や第三のビールも、価格差が縮まることで選び方に変化が生まれることが考えられます。
市場全体や景気への効果
酒税一本化は、市場全体や景気にも影響を及ぼす可能性があります。価格差の縮小により消費者の購買行動が変化し、製造や販売戦略の見直しが進めば、市場競争の健全化が期待されます。また、税収が安定することで国家財政における酒税の透明性と公平性も高まります。制度の安定化は、社会全体にとっても大きなメリットといえるでしょう。
他ジャンルのお酒はどうなる?
ワインや日本酒などの醸造酒は、すでに2023年10月に1キロリットルあたり10万円に統一済みです。一方、焼酎やウイスキーなどの蒸留酒は、引き続き種類ごとに異なる税率が適用されています。なお、アルコール度数の低い蒸留酒に適用されていた特例税率は、2026年10月に引き上げられる予定です。
まとめ
酒税一本化は、ビール・発泡酒・第三のビールを中心に税率を統一する改正です。消費者・メーカー・行政の三者に影響を及ぼし、市場全体の健全化や税収の安定化をもたらします。今後の酒類市場は、価格競争ではなく、これまで以上に味やブランド、品質で勝負する方向へシフトしていきます。消費者にとっても、自分の嗜好に合った商品を選びやすくなり、楽しみの幅が広がるでしょう。
2級FP技能士
広告代理店勤務を経て、フリーライターとして6年以上活動。自身の投資経験をきっかけにFP資格を取得。投資・金融・不動産・ビジネス関連の記事を多数執筆。現在はフリーランスの働き方・生き方に関する情報も発信中。
(提供元:Mattrz![]() )
)